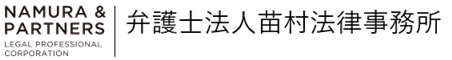特許発明が製品の一部にのみ実施される場合の 特許法102条1項に基づく損害算定 (2020年6月22日)
特許発明が製品の一部にのみ実施される場合の特許法102条1項に基づく損害算定
-「美容器」事件 知財高裁大合議判決-
弁護士 田中 敦
1 はじめに
本年2月28日、知財高裁が、特許法102条1項に基づく損害算定方法についての大合議判決(以下「本判決」といいます。)を下しました。本判決は、昨年の同条2項及び3項に基づく損害算定についての知財高裁大合議判決[1]に続く重要な判示であり、今後の実務に大きな影響を与えるものと考えられます。
本判決では、特許法102条1項を巡る多くの論点への判断が下されていますが、紙面の関係上、本稿では、本判決と原審判決[2]との損害額の差異に大きく影響したと考えられる、特許発明が製品の一部にのみ実施される場合の損害算定の判示について述べることとします。
2 事件の経緯
控訴人(原審原告)は、美容器(いわゆる「美顔ローラー」)に関する特許権(特許第5356625号等、以下「本件特許」といいます。)を有していました。控訴人は、被控訴人(原審被告)が本件特許を侵害する製品を販売しているとして,特許権侵害を理由にその差止めや損害賠償を求めました。
原審判決は、特許権侵害を認めつつ、特許法102条1項[3]に基づく損害算定にあたり、本件特許の特徴部分は原告や被告の販売する製品の一部に関わるに過ぎないという事情を、寄与度(特許発明の利用が被告の製品に寄与した割合)という概念を用いて、算定根拠となる原告の限界利益に寄与度10%を乗じました。加えて、同項但書きに基づき、被告による譲渡数量のうち5割を原告みずから「販売できない事情」があるとして推定覆滅を認め、最終的な損害額を約1億0735万円としました。
原審判決に対し双方が控訴し、知財高裁では、原審判決による算定方法が妥当であったか否かが争われました。
3 知財高裁による判断
(1)特許法102条1項
特許法102条1項は、特許権侵害による損害額推定の規定であり、侵害者が侵害品を販売していた場合には、侵害者による侵害品の譲渡数量に、もし侵害行為がなければ特許権者が販売することができた物の単位数量あたりの利益を乗じた額を、特許権者の実施能力に応じた額を超えない程度において、損害額と推定すると定めます。ただし、例えば、価格や販売態様が大きく異なる等の理由から、仮に特許権者が販売していれば同数量の販売は困難であった場合、同数量の「販売ができない事情」があるとして、当該事情に相当する金額が推定額から控除されます。
ただ、本件のように、特許の特徴部分が製品の一部にのみ実施されるという事情がある場合、条文上からは、どの要件の下で当該事情を考慮すべきかは必ずしも明らかではありませんでした。この点、主な考え方として、当該事情を特許法102条1項の「単位数量あたりの利益の額」の算定にあたり考慮する説(本文説)、同項但書きの「販売ができない事情」として考慮する説(但書説)、それらいずれとも異なり民法709条の因果関係の問題として別途考慮する説(民法709条説)の3つに分かれていました。
なお、特許法102条1項は、令和元年特許法改正により改正されましたが、本判決の判示は改正後の条文にも妥当し得るものと考えます。
(2)知財高裁による損害の算定方法
まず、知財高裁は、本件特許が製品の一部にのみ実施されるという事情がある場合でも、製品販売による特許権者の限界利益の全額が逸失利益として事実上推定されると判示しました。ただし、本件特許が利益の全てに貢献しているわけではないことから、当該事情を、限界利益の事実上の推定を一部覆滅させるものであるとして、限界利益から約6割を控除しました。この判示は、限界利益がそのまま「単位数量あたりの利益の額」とまず推定されることを前提に、製品の一部にのみ実施されるという事情により限界利益のうち一部の推定を覆して最終的な利益の額を決定するものであり、3つの学説のうち本文説を採用したものと理解できます。知財高裁は、寄与度という概念を用いた原審の算定方法を「根拠がない」と否定し、寄与度による利益のさらなる減額を認めませんでした。
他方で、知財高裁は、両製品の価格の違い等から、控訴人みずから同数量の「販売ができない事情」があるとし、原審と同じく5割の推定覆滅を認めました。もっとも、知財高裁は、原審が寄与率の検討において減額要素として認めた一部の事情(本件特許の特徴が需要者の目に触れる部分でないこと、代替技術の存在)を減額要素として認めませんでした。
以上の算定方法に基づき、結論として、知財高裁は、原審判決の4倍以上となる4億4006万円の損害を認めました。
(3)本判決による実務への影響
従前の裁判例では、特許発明が製品の一部にのみ実施される場合の損害算定について判断が統一されていませんでした。このような状況下で、本判決が、本文説に依るべきことを判示したことは、今後の実務に与える影響は大きいと考えます。
また、寄与度という概念を用いることを否定した点も注目されます。「寄与度」とは、特許法102条各項に基づく損害算定にあたり、特許発明の貢献度に応じて損害額を適切な範囲に限定するために、一部の裁判例や学説により導入されたものです。しかし、何を評価基準とするか、寄与度(又は非寄与度)の立証責任の所在等について見解が統一しておらず、仮に特許権者が利益の額に加えて寄与度をも立証しなければならないとすれば、立証責任を容易にしようとした同条の趣旨に反する等の問題点が指摘されていました[4]。本判決の算定方法は、特許発明による貢献が限定的であることを、寄与度ではなく、限界利益の事実上の推定の覆滅事由と捉えることで、侵害者が反証すべきであることを明確にした点においても一定の意義があると思われます。
もっとも、本判決の算定方法によっても、利益の推定覆滅のためにどのような要素をどの程度重視するかは、いまだ明らかにはされていません。本判決が原判決の4倍もの損害額を認めた理由についても、算定方法の違いにのみ起因するとは直ちにいいきれず、さらなる検討が必要です。知財高裁としては、昨年の知財高裁大合議判決[5]に続けて、賠償額が低額に過ぎるとの批判もあった損害論に関するルールの明確化を進めており、特許法102条1項の改正と相まって、賠償額の高額化へ作用する可能性もあります。損害論に関しては、懲罰的賠償や利益吐き出し型賠償の導入の是非についての議論も続けられているところ、知財高裁の示した新たなルールが訴訟の結果にどの程度影響するかを見極めるためには、引き続き今後の事例に注目する必要があります。
以上
[1] 知財高裁令和元年6月7日判決(「炭酸パック化粧料」事件)
[2] 大阪地裁平成30年11月29日判決
[3] 令和元年特許法改正前の条文が適用されており、本稿でも特にことわりのない限り同改正前の条文を指すものとします。
[4] 田村善之『特許権侵害に対する損害賠償額の算定 −裁判例の動向と理論的な分析−』(パテント・2014年)141頁
[5] 前掲注1・知財高裁令和元年6月7日判決