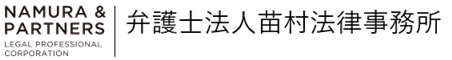遺言書と遺留分の話(2013年10月9日)
遺言書と遺留分の話
弁護士・ニューヨーク州弁護士 苗村博子
1. 遺言書不作成のススメ
家族の関係が希薄になりつつあり、また一人で老後を迎える人達が増えてきたこともあって、近頃、遺言書作成の色々な案内がありますね。弁護士は、遺言作成のお手伝いも業務の一つですので、本当はこんなことをいってはいけないのかもしれませんが、相続人の一部に財産を集中させるような遺言書は作成しない方がいいというのが私の持論です。
遺言書は、後で相続人同士の争いを避けるためのもの。なぜ反対するの?と思われるかもしれません。しかし、現実には、なかなかそううまくはいきません。遺言書に書いたとおりに財産が分配されるとは限らないからです。
2. 遺留分の制度
(1) 遺留分とは?
日本には、遺留分という制度があり(民法1028条以下)、相続人が父母や祖父母といった直系尊属である場合には相続財産の3分の1,配偶者、子供(子供が先に死亡していた場合は代襲相続人としての孫)には、相続財産の2分の1までが遺留分として認められ、この遺留分を害するような遺言に対しては、遺言書に書かれた遺贈や贈与の減殺を請求できます(民法1031条)。減殺とは、その効力を遺留分額に限って、なくしてしまうとうことです。従って遺言者の思惑とは異なり、遺言どおりに相続財産が分けられるとは限らず、遺留分減殺請求がなされることも多く見られます。
その場合には、なまじ被相続人の意思が遺言書に記載されているがために、いわゆる相続争いは激化しがちです。遺留分減殺請求をする側からすれば、自分の知らないところで自分に不利な遺言書が作成されたということで、遺言者に裏切られたような気持ちになることが多く、かといってその時点では遺言者は既に亡くなっているので、勢いその怒りの矛先は、遺言書で有利に取り扱われている相続人に向かってしまいます。
私もやはり、相続人間での激しい争いをいくつか見てきました。双方共に、大変に消耗されていく様子を見るのは弁護士としてもつらいものがあり、なんでこんな罪作りな遺言書を作ったんだと、お会いしたことのない遺言者(被相続人)を恨みたくなるような気持ちになることもあります。遺言書は、文書として残りますので、遺言者の最後の意思として重く扱われますが、ご高齢の方の場合などは特に、その時々で考えが変わることも多く、確固たる最終意思が記載された遺言書といえるものは、本当は少ないように思います。
というわけで、私はご依頼者には、なるべく、相続人の一部を利するような遺言書は作らないようにとアドバイスしています。自分がいなくなってからのことまで心配せず、後は残った人に任せましょうと。
(2) 遺留分がなぜ認められているのか?
自分が築いた財産なのに、なぜ自分の思い通りに処分できないの?と遺留分の制度自体を不審に思われるかもしれません。この制度は昭和27年の民法改正で導入されました。それまでの家督相続が「家」制度につながるという理由で諸子均分相続制度に変更すべしとの意見に加え、配偶者保護の要請から、このような制度が規定されたのです。また遺言者の財産といっても家族で築いたものという点もあることから、潜在的に相続人は、遺言者の財産に一定の権利を有しているとの考え方もその背景にあります。
私自身は配偶者間では、この点への配慮はもっともだと思います。夫婦間では、一方名義の財産も二人で築き、守ってきたと言える場合が多いからです。しかし、子供に関しては、遺留分の制度が必要かは疑問に思っています。これらの人達が、財産の形成に関与することは現代では稀だからです。
(3) 遺留分減殺請求権の行使方法
このような遺留分の制度ですが、現実にその権利を行使する減殺請求については、相続の開始と減殺ができる遺贈や贈与があったことを知った時から1年以内に請求しなければ時効消滅してしまいます(民法1042条)。遺贈とは相続人や第三者に遺言書で以て財産の一部または全部を贈与することをいいます。遺留分減殺請求の対象になる贈与は死亡前1年以内のものに限られます(民法1030条)。また減殺請求できる贈与と遺贈がある場合、遺贈から先に(民法1033条)、そして時系列的に新しいものから先に減殺請求の対象となります(民法1035条)。
3. 遺留分の放棄と推定相続人の廃除
このように遺留分の制度は複雑で、また上では触れませんでしたが、その計算方法も様々な考え方があり、どうしても紛争化すると長期、深刻なものになってしまいます。それも私が遺言書不作成のススメをする理由です。
それでも,どうしても諸事情で財産を一定の人に集中させる必要がある・・・という場合には、方法がないわけではありません。被相続人の生前の相続放棄は認められていません。被相続人に対して、①虐待をし、②重大な侮辱を加え、または③その他著しい非行がある推定相続人には、被相続人は家庭裁判所に相続人の排除の請求をすることができますが(民法892条)、②、③のような事情については、よほどのことがないと裁判所では廃除が認められません。
そこで、一定の人に財産を相続させる、遺贈するというような遺言書を書き、それに対して遺留分を持つ相続人に、あらかじめ遺留分の放棄をしてもらうことが考えられます(民法1043条)。
しかし、この放棄は、家庭裁判所の許可がなければ効力を生じません。裁判所の許可の基準については、必ずしも明確ではありませんが、①放棄が放棄者の真意に出たものであること、②放棄に合理的・必要的理由があること、③放棄に対する代償財産の提供があること等が要素として検討されているようです。基本的には、真意に基づくものか、裁判所が確認できればよいのではないかと思っています。