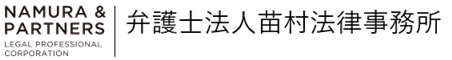独禁法改正―裁量型課徴金と秘匿特権(2019年8月28日)
弁護士 苗村 博子
1.改正の趣旨
独禁法には、さまざまな規制が定められています。いま、大きな話題となっているのは、いわゆるGAFAといわれるデジタルプラットフォーマーが、その利用者に対して課しているさまざまな制約が独禁法に抵触しないかという問題です。この原稿を書いている最中にも公取委が独禁法を企業対個人にも適用し、現在の法律においてもその圧倒的案シェアにより、プラットフォームを利用する者に自らの規律を一方的に押し付けているような場合に、優越的地位の濫用にあたるとする指針案を出したと日経新聞に報道されました。今回の改正の次には、このプラットフォーマー規制について、立証の容易化その他が検討され、規制が強化されるものと考えられます。
前置きが長くなりましたが、今回の改正は、それとは異なり、課徴金が最も効率よく課されている不当な取引制限、すなわち、カルテルの課徴金の額を公取委の裁量で決められるようにしようというものです。課徴金が導入された昭和52年以降、課徴金の対象行為は拡大されてきましたが、その執行が強化されたのは、2005年に課徴金減免制度が導入されて以降です。この減免制度については、現在は、一番目の申立者には、全額免除、2番目の者には、50%免除、3番目の者には30%免除というように、免除額が、羈束されており、公取委には裁量権がありません。米国では、課徴金の免除制度に当たるリニエンシーは、最初にこれを申し立てた者のみにしか与えられませんが、2番目の者はセカンドインと呼ばれ、その協力の如何により、減じられる罰金額について司法省の裁量幅は相応に広く、対象企業は少しでも減じてもらうため、必死に情報提供を行います。そして提供された情報から、司法省は、新たなカルテルを見つけ出すのです。
このように課徴金について、公取委に一定の裁量権を認め、協力すれば課徴金を減じ、非協力であれば、課徴金を増額するとして、対象事業者にプレッシャーをかける、いわば米国司法省の捜査手法を取り入れようというのが、今回の改正の趣旨なのです。
2.改正の骨子
(1) 課徴金制度の見直し
これまでは、課徴金の算定の基礎となる期間は3年まででした。米国では反トラスト法違反には消滅時効が適用されないため、カルテルの開始時まで遡れるのとは、大きな違いで、米国の罰金額と日本の課徴金額に大きな差異があったのは当然のことです。今回調査開始日から10年まで遡れるように改正されます。その売上額の10%が課徴金額となりますが、算定基礎自体も追加され、①談合の際に、応札しないことによる対価や、②対象となる商品や役務に関連する業務によって受けた売上額も加算され、③違反者の売上だけでなく、カルテル等の指示を受けて行動した、子会社等の売上も加算対象となります。
(2) 課徴金減免制度の見直し
改正法は、これまでの順位のみによる低減率を小さなものとし、調査開始前であれば、1番目の者には従前どおり全額免除を与えますが、2番目に申請した者に20%減、3~5位に10%減、6位以下には5%とし、調査後であれば、最大3社に10%、それ以外には5%の低減率と定めました。目玉はそのほかの低減率で、この基礎となる減率に加え、調査協力の度合いに応じ、これにプラスして調査前であれば、最大40%の低減率が、調査後でも最大20%の低減率が用意されています。
また現在は、違反行為の繰り返しや、違反行為の主導者については、一方だけがあれば、50%、両方があれば100%の加算が加えられますが、この改正で、これらに加え、隠ぺいや、仮装などの調査妨害もこの割増算定の対象とされることになりました。
協力する者には、2番であっても場合によっては60%の減算が可能となりますし、初めての検挙で指導的立場でなかったとしても、調査妨害があれば、50%割増加算がなされるということになり、まさにあめとムチでの対応がなされるのです。
一定の裁量権を持つことは、公取委の悲願ともいえるものでしたので、公取委としては、今回の改正は、その法執行力の強化に重大な影響を及ぼすものと理解しているはずです。
3.弁護士依頼者間の秘匿特権の導入
公取委は、法律ではなく、規則で主だった内容が明記されることとして、課徴金減免制度を用いた法執行の効率的な運用と適正手続を確保する観点から、一定の弁護士と依頼者の通信についての秘匿を認めることとしました。事業者から、弁護士への相談内容、もちろん最初の段階では、事業者は自社の行動が独禁法違反になるのかどうかという点からの相談となりますが、相談にかかわる弁護士との様々なやり取りは、秘密として、公取委から求められても提出を拒むことができる制度の導入が検討されています。いまだ規則案が公表されていないので、議論はこれから始まるのですが、公取委としては、この制度は、独禁法違反行為全般に及ぶものではなく、カルテルについてのみ、独禁法47条の強制調査権に基づき、提出を求められた際に、これらの通信についての文書が調査の対象とならないとするようです。公取委が挙げている例を申しますと、事業者からの相談文書、弁護士からの回答文書、弁護士が行った社内調査に基づく法的意見が記載された報告書や、弁護士が出席する社内会議でその弁護士との間で行われた法的意見についてのやり取りが記載された社内会議メモなどが挙げられています。電子メールがこの中に入るのかが明確ではありませんが、ご依頼者との多くの通信が電子メールで行われている現在、これが対象とならないようでは、ほとんど意味がありません。この点はこれからも日弁連でも強く申し入れをしていく必要があるところと考えています。
もちろん、秘匿する特権ですから、これらの電子メールが、CC等で社内の人とはいえ、あまりに多くに送付されているようでは、秘密性が疑われれてしまいます。むやみにCCに入れて送付するのはよくありません。
また公取委と弁護士の間で、秘匿特権の対象となるかについて、見解が分かれた時には、まずは、書類に封をした状態で、公取委に渡し、これを、事件を担当する審査官ではなく、公取委内の官房に置かれた判別官がこれらの書類の要件の充足性について審査を行うとしています。電子メールのようなデータの取扱については、公取委の規則案、細則案を見ないとわかりません。米国では、まずは、司法省は、電子データをすべてコピーして持ち帰りますが、直ちに捜査担当検事がみるのではなく、事業者側で、自らベンダーに依頼してフォレンジック機能を用いて、関係するデータだけをサーチワード等で、検索するとともに、これらの検出されたデータの中から、弁護士が秘匿特権対象文書の記録(ログ)を作成して、検察官に提出し、検察官は納得すれば、対象証拠にはアクセスしません。争いになった場合には裁判所に判断を求めることができます。公取委も判別官と弁護士の意見が分かれた場合には、行政事件訴訟法の規定に基づいた取消訴訟の提起が可能だとしています。
公取委では、今回の秘匿特権らしきものの導入は、事業者側の要請に格別の配慮をしたものとして、国際的にもアピールしたいとの考えの様ですが、世界では全く逆に評価されているようで、本来すべての事件で、依頼者と弁護士の通信は秘密であるべきと考える英米の弁護士には、このような一部にだけ、しかも課徴金減免制度を利用した者にのみ秘匿特権を認めるということは、ほかには認めないものと考えるきらいがあります。米国の弁護士から、よく、あなたには弁護士依頼者間の秘匿特権がないのでは?と言われるのに閉口しています。私はNY州の資格もあるから大丈夫と答えていますが、そのような答えをしなければならないところに日本の弁護士としてのもどかしさを感じて仕事をしております。