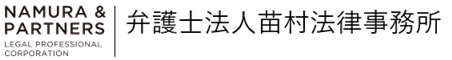企業年金の受給者減額の可否に関する判例の動向(2010年11月16日)
企業年金の受給者減額の可否に関する判例の動向
弁護士 田中 敦
【はじめに】
企業年金とは、国民年金や厚生年金などの公的年金に上乗せする形で、民間企業が退職者に対し独自に支給する形態の年金をいいます。ところが、近年、景気後退や業績の悪化を理由に、多くの企業で企業年金の支給額を減額しようとする動きが見られるようになりました。そのような状況の中で、今年に入り、退職後に企業年金を受給している者の支給額を減額することができるか否かが争われた事案で、一方的な減額が認められないとして、企業側の敗訴とする最高裁判所の判断が相次いでいます。今回は、企業による一方的な企業年金の減額が認められないとした最高裁平成22年3月16日第三小法廷判決(判タ1323号114頁)及び最高裁平成22年6月8日第三小法廷決定を参考に、企業年金の減額の可否について検討します。
【平成22年の最高裁判所による裁判】
1 最高裁平成22年3月16日第三小法廷判決(「X銀行事件」)
この事案は、銀行の取締役を退任した原告が、株主総会決議を経て、当時の役員退職慰労金規程に従い退職慰労年金を受給していたところ、その後に当該規程の廃止決議がされ、年金の支給が打ち切られたため、被告である銀行に対し、未支給分の退職慰労年金の支払等を求めたものです。
被告である銀行は、退職慰労年金における集団性、画一性等の制度的要請から、一定の場合には退任取締役の同意なく契約内容を変更することが許されるなどと主張し、原告の主張を争いました。
原判決では、被告主張の理由に依拠し、一定の場合には、規程の改廃の効力を退職した取締役に及ぼし、その退職慰労年金請求権を減額し又は消滅することができると判断して、原告の請求を棄却しました。これに対し、最高裁は、本件退職慰労年金の額及び支給方法は、原告の退職時に原告と会社との間の契約内容として確定していたとし、年金の制度的要請という理由のみをもって、原告の同意なく、本件規程の廃止の効力を及ぼすことはできないと判断して、原判決を破棄・差戻しとしました。
2 最高裁平成22年6月8日第三小法廷決定(「NTT事件」)
この事案は、原告会社が、確定給付企業年金法に基づき実施している企業年金について、受給権の内容等に変更を生じさせる年金規約の変更をするために、厚生労働大臣の承認を求める申請をしたところ、厚生労働大臣が、上記規約変更は、受給権者等に対する給付の額を減額する場合に該当し、減額のために必要とされる要件を満たしていないとして、会社に対し当該規約変更を承認しない旨の処分を行いました。そこで、原告会社が、その処分の取消しを求めたものです。
原告は、①給付額減額の要件を定める法令の規定が無効である、②本件申請にかかる規約変更が「給付の額を減額する」場合に該当しない、③仮に②において「給付の額を減額する」場合に該当するとしても、本件の規約変更は法令に定める要件を満たすなどと主張し、不承認処分の取消しを求めました。
第一審判決及び原判決は、ともに原告の主張を全て退け、本件処分は有効であると判断しました。これに対し、原告は上告受理を申し立てましたが、最高裁はこれを却下しました。
【検討】
1 企業年金の受給者減額が認められた事例
以上の2件の判例に対し、企業年金の受給者減額が認められた事例としては、最高裁平成19年5月23日第一小法廷決定(「松下電器産業事件」)があります。
この事案は、被告会社において、従業員の退職にあたり、退職金の一部を拠出して会社との間で年金契約を締結し、会社がこれを運用して年金を支払うという企業年金制度が採られていたところ、会社が給付利率の引下げを決定したため、被告会社の元従業員である原告が、当該決定の効力を争い、引下げがなければ各支給日に支給されたであろう金額と実際の支給額との差額の支払いを求めたものです。
このケースでは、退職者に支給される年金額算定の基礎となる約定利率が年7.5%~10%と高水準に設定され、実際の運用利回りとの差額は会社の収益から賄われていました。被告会社は、市場利回りの低下や業績悪化等を理由に、約定利率を一律2%引き下げる内容の年金規程の改定を行いました。ここで、被告会社の年金規程には、将来、経済情勢等に大幅な変動があった場合には規程の全般的な改定または廃止を行うという旨の、改廃条項が置かれていました。
第一審判決及び原判決は、当時の被告会社の経済状況からすれば、本件規程の改定は上記改廃条項の要件を満たすことが認められるとして、ともに原告の請求を棄却しました。これに対し、原告は上告受理を申し立てましたが、最高裁はこれを退けました。
2 企業年金の種類
企業年金の種類は、大きく分けて、自社年金型と外部積立型に区分できます。
自社年金型とは、年金給付のための資産を企業外に取り分けていない制度のことをいいます。この制度を対象とした法令上の規制は存在せず、基本的には各企業が自由に制度を設計できることとされています。上記のX銀行事件及び松下電器産業事件の各事案における年金制度が、この自社年金型に該当します。
一方、外部積立型とは、厚生年金基金や確定給付型企業年金のように、拠出する掛け金を外部に積み立てて、会社の資産とは別個に管理する制度をいいます。この類型の企業年金については、厚生年金保険法や確定給付企業年金法の規制に服することとなります。上記のNTT事件の事案における年金制度が、この外部積立型に該当します。
3 検討
企業年金の受給者減額の可否については、当該企業年金が、自社年金型か外部積立型かにより、その判断枠組みが異なります。
(1) 自社年金型
まず、自社年金型の企業年金の場合、法令または監督官庁による規制が予定されていないことから、自社年金制度を定めた規程の改廃の可否については、専ら民法、労働法の解釈に委ねられると考えられています。これまでの裁判例からは、その一般的な判断枠組みは、①年金支給額の減額について、契約(規約)上の根拠があるといえるか、②実際に行われた減額の内容について、必要性・相当性があるかにより判断されるものとされています[1]。
松下電器産業事件では、①会社の年金規程に当該規程の改廃条項が置かれていること、②改定以前の約定利率が高水準に設定されており、市場利回りの低下や会社の業績悪化といった事情からすれば、規程の改定もやむを得ないものといえることから、減額が認められています。
一方、X銀行事件では、①会社の退職慰労金規程に改廃条項はありませんでした。そこで、原審は、規程の条項の解釈を経ることなく、年金制度の制度的要請を理由に、減額を有効と判断しました。これに対し、最高裁は、年金の支給は会社と退職取締役との間の契約に基づいて行われるという個別契約的側面を重視し、契約(規約)中に減額の根拠が認められない以上、会社が一方的に支給額を減額することはできないと判断したものと考えられます。
(2) 外部積立型
外部積立型の企業年金の場合、受給者減額を内容とする規約変更については、法令上、厚生労働大臣の承認・認可が必要とされています。その承認・認可の要件は、①企業、基金の財政状態が悪化していること、②受給者の3分の2以上の同意を得ること、③希望者には一時金での清算を認めることと定められています。
上記①の要件に関しては、確定給付企業年金法施行規則5条2号の「経営の状況が悪化したこと」について、どのように解釈すべきかが問題とされてきました。この点、NTT事件では、「受給権者等に対する給付減額が許容されるためには、単に経営が悪化しさえすれば足りるのではなく、母体企業の経営状況の悪化などにより企業年金を廃止するという事態が迫っている状況の下で、これを避けるための次善の策として、給付の額を減額することがやむを得ないと認められる場合に限られる」と判断した原審判決を支持しており、同号の要件該当性に関し最高裁が初めて判断を示したものとして、先例的意義を有するものといえます。
【終わりに】
今年の最高裁による企業年金の受給者減額の可否の判断は、減額についての契約(規約)上の根拠及び減額の必要性を、より厳格に要求したものと考えられます。今後、企業が年金制度を構築するにあたっては、将来、支給額を減額しなければならざるを得ない状況が生じた場合を見据え、年金規程に減額の根拠となる条項を置くことが望まれます。また、企業がすでに実施されている企業年金の支給額を減額するにあたっては、年金規程の内容、減額の必要性及び減額の程度について、より一層慎重に検討することが求められるものと思われます。
[1] 森戸英幸=君和田伸仁=大沢英雄「企業年金(受給者減額)」(ジュリスト1331号147頁)