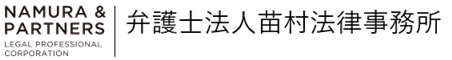ウィーン動産売買法(CISG)の適用問題(2009年8月18日)
ウィーン動産売買法(CISG)の適用問題
弁護士 渡辺惺之
6月17日に当事務所が開催したウィーン国際物品売買条約に関するセミナーには多くの方が参加して下さり、幸いに好評に終わった。セミナー後に、参加者の方から質問を頂いたが、そのかなりの部分がCISGの適用に関する質問であった。セミナーでは、時間の切迫もあり、CISGの適用に関わる問題点については要点のみをやや単純化してお話しした。そこでCISGの適用に関わる問題、適用排除にはどうすればよいのか、CISGの適用・適用排除のメリット、デメリットについて、改めて説明をさせていただくことにした。
1.適用範囲の問題?
一般に新立法があったり法改正があった場合、その適用問題は常に関心を呼ぶ問題の一つとなる。それが国内法改正であれば、適用問題として論じられるのは、新規定の適用射程などと呼ばれることがある事項的な適用範囲と、何時から新規定が適用されるかという時間的な適用範囲の問題である。CISGについても、この事項的な適用範囲と時間的な適用範囲は問題となるが、これらについては明文の規定がある。
2.CISGの時間的適用範囲
これは新法が施行される場合には常につきまとう問題といえるが、新法が発効する時点をまたぐ形になる法律関係、CISGでは売買契約、特に継続的な契約についての適用問題である。CISGでは100条に明文の規定が置かれ、1条が規定する適用条件に関わる国について条約が発効した日を基準としている。日本に関しては、原則的に発効日である8月1日以降に締結された契約に適用されるが(同条(1))、契約の申込が同日以前になされていた場合は、CISGの中で契約の成立に関する第2部の規定は適用されない(同条(1))。継続的な製品供給契約等のケースで、CISGの発効日以前に基本契約の締結があり、それに基づき個別の注文と供給がなされる契約事例が問題となるが、個別の発注が新たな売買契約の締結と見られる限り発効日以降の個別契約はCISGの適用対象となる。しかし、個別の発注と供給がCISG発効前に締結された基本契約の履行と解される場合は、発注が8月1日以降であってもCISGの適用はないと解される。
3.CISGの事項的適用範囲
事項的な適用範囲についても、CISGは2条以下に明文で規定している。適用対象は動産売買契約に限られるが、その中でも消費者売買、競売、有価証券の売買、船舶や航空機などの売買、電気の売買は除外される(条約2条)。また、CISGが規定している事項は、動産売買に関する契約の成立並びに売買契約から生じる売主及び買主の権利・義務に関わる事項に限られ、特に契約や契約条項の有効性(適法性)や、売買目的物の所有権に関する事項は規定対象外である(条約4条)。同じく売買目的物による人身被害に関する責任の問題も適用対象外と規定している(条約5条)。
CISGは動産売買の全ての問題に関する契約特別法ではなく、その成立と売主及び買主の権利義務に関する事項を中心とした部分的な特別法である。従って、CISGが適用される場合でも、国際契約の準拠法によらなければならない場面は多くあり、これまでと同じく契約準拠法に注意を払う必要があることに変わりはない。
4.CISGの場所的適用の問題
CISGに関して、特にその適用が問題となる局面は、上で述べたのとは異なる局面、一般に場所的適用範囲と呼ばれる問題局面である。これに関しては見解が分かれる。もともと場所的適用範囲とは日本法の適用される範囲はどこまでかという意味で、通常の国内的な事件の場合には意識されないが、国境を越えた私法上の法律問題に関して問題となる。現代の法学では国際私法と呼ばれる分野の問題である。
国際私法は各国の私法がそれぞれ独立対等に併存している状態の中で、国際的な法適用の安定を理念とした法システムということができる。複数国にまたがる法律問題について関係各国においてそれぞれ自国の私法を適用し判断すると、国毎に私法が異なるため法的判断が国際間でバラバラになり著しい法的不安定を生じる。これは国際的な人や物の移動・流通の大きな障害になる。そこで、関係国の裁判所が当然に自国の私法を適用するのではなく、問題となる法律関係に最も密接に関係する国の私法法規を準拠法として適用するシステムを採用することで、関係国裁判所において適用される私法について調和が得られるというシステム認識に基づき、国際的な私法事件について適用すべき準拠法の調整をはかろうというのが国際私法である。日本では「法の適用に関する通則法」がこれに当る。
ところで、この準拠法を選択し適用するシステムとは別に、国境を越えた法律関係について法的安定をもたらすもう一つの有力な方法として、私法の統一という手法もある。各国の私法法規を統一することができれば国際的な法的安定が達成される。CISGはまさにこの一例なのである。CISGの場所的適用をめぐる議論は、基本的な国際私法システムの中で、この統一法の適用をどう位置づけるかということから生じている。
CISGについて直接適用説とか国際私法を介さない適用説とか称される立場は、統一私法であるCISGは国際私法システムとは別枠で適用されると解する立場といえる。これによると、先ずCISG1条により適用を検討し、CISGの適用がない場面でのみ国際私法による準拠法の決定が行われる。これと異なり、CISGの1条自体が国際私法の規定、いわば法の適用に関する通則法の特則のように考える立場もあり得る。実際の適用結果に両説に違いはほとんどないが、CISGの適用排除するためにはどのような文言が必要かという点に関して違いが生じ得る。直接適用説では原則的にCISGの適用排除の明文が必要になるが、国際私法説ではCISGを採用していない国の法を準拠法として合意することでも足りることになる。実務的には、CISGについて日本の裁判所の判例がまだない状態であり、適用を排除しようとするのであれば、売買契約が1条の規定に該当する場合は準拠法条項の中にCISGを適用しない旨の文言をはっきり書き込んでおくことが無難といえる。
5.CISGの適用排除すべきか?
CISGの適用を排除した場合は、その動産売買契約については全て合意された準拠法が適用される。準拠法合意がない場合は、裁判が行われる国(法廷地国)の国際私法規定により準拠法が定まる(日本の場合は通則法8条によれば原則的には売主の常居所地国の法)。CISGの適用を排除しなかった場合で、同1条に相当する場合は、3.で述べた事項的範囲ではCISGが適用され、それ以外の部分では準拠法が適用されるという、法の分割適用が生じることになる。
CISGの適用を排除すべきかの判断は、個別の事情に異なり、一概に断定することはできない。CISGは国際的な統一法ではあるが、その解釈については加盟国裁判所により差もある。日本はCISGが発効したばかりで、まだ判例もなく不確定な要素もある。CISGは契約法システムとしては評価が高いが、現行民法と制度的に異なる点も少なくない。これらの要素をどう評価するかがポイントといえよう。
一般的にはエキゾチックで内容も把握しきれない国の法が準拠法となる場合、或いは、相手方所属国が自国法を準拠法とすることを譲らず当該国の裁判所で訴訟をする可能性があり、その場合、自国利益保護的な判断がなされる傾向のある国との関係では、CISG適用の可能性があれば、国際的な統一的解釈のベクトルが作用する可能性があり得るので、CISG適用を合意するメリットがあるように思われる。